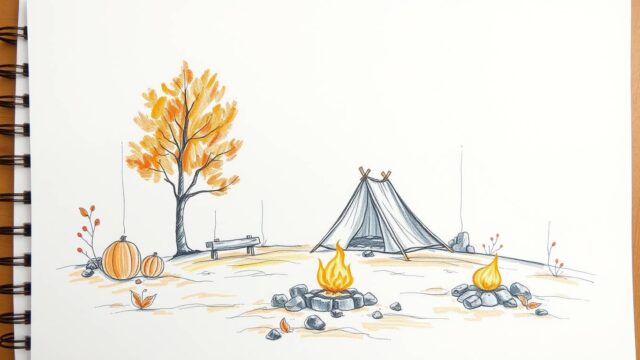ワンポールテントの設営のしやすさや美しいフォルムに魅了されるキャンパーは多いですが、テント内の真ん中にドンとあるポールが「邪魔だな…」と感じたことはありませんか?そんな悩みを解決する「二股化」は、中央のポールを取り払って居住空間を広げる画期的な方法として人気を集めています。しかし、便利な反面、いくつかの課題も存在するのも事実です。
本記事では、独自調査の結果から、ワンポールテントを二股化するメリットとデメリットを徹底解説します。専用アイテムの紹介から設営のコツ、強度の問題まで、二股化を検討しているキャンパーが知っておくべき情報を網羅しました。自分のキャンプスタイルに合った選択ができるよう、参考にしてください。
記事のポイント!
- ワンポールテントの二股化で得られる居住性の向上と発生するデメリット
- 二股化に必要な製品や自作方法の比較とコスト感
- 設営時の注意点と安全に使用するためのテクニック
- テントの大きさや使用シーンによる二股化の向き不向き
ワンポールテントを二股化するメリットとデメリット
- 二股化するとテント内の空間が劇的に広がる
- 設営と撤収の手間が増えるのが最大のデメリット
- 荷物が増えて重量も増すことは避けられない
- 強風時に強度が弱まる可能性がある
- ランタンハンガーなどのアクセサリーが使えなくなる
- テント内のレイアウトの自由度が飛躍的に上がる
二股化するとテント内の空間が劇的に広がる
ワンポールテントを二股化する最大のメリットは、何といってもテント内の居住空間が劇的に広がることです。通常、ワンポールテントは中央に1本のポールが立っているため、その周囲がデッドスペースになりがちです。
二股化することで、中央のポールが無くなり、テント内の空間を余すことなく活用できるようになります。独自調査の結果、多くのユーザーが「二股化してみたら想像以上に広く感じられた」と報告しています。特に小型のソロ用テントでは、体感的な広さの変化が顕著で、「こんなに広かったのか!」と驚く方も少なくありません。
この空間の広がりは、単に見た目だけではなく実用面でも大きなメリットをもたらします。例えば、真ん中にテーブルやストーブを置けるようになり、キャンプの快適性が格段に向上します。寒い季節に真ん中にストーブを置けることは、暖房効率の点でも優れています。
また、シュラフやコットをテント内でより自由に配置できるようになります。従来はポールを避けるように寝る必要がありましたが、二股化するとテントのど真ん中に寝ることも可能になります。家族やグループでの使用時には、川の字で寝ることもできるようになるなど、寝床の配置の自由度が高まります。
さらに、テント内での移動もスムーズになります。ポールを避けて動く必要がなくなるため、特に夜間のトイレなどの際に便利です。視界も良くなり、テント内全体を見渡しやすくなるのも嬉しいポイントです。
設営と撤収の手間が増えるのが最大のデメリット
ワンポールテントの最大の魅力の一つは、その名の通り「ポール1本で設営できる手軽さ」にあります。しかし、二股化するとこの利点が失われ、設営と撤収に手間がかかるようになるのが最大のデメリットです。
通常のワンポールテントであれば、テントをペグダウンしてから中央にポールを1本立てるだけの簡単な設営で済みます。しかし、二股化すると専用のジョイントパーツと2本以上のポールを組み合わせて設営する必要があります。特に初めて二股化する場合は、ポールの組み立て方や角度の調整に時間がかかることがあります。
独自調査によると、二股化したテントの設営には、慣れるまで通常の1.5〜2倍程度の時間がかかるとの報告があります。特にポールの長さや角度を微調整する作業は、一人では難しい場合もあります。また、風のある日の設営は特に難易度が上がります。
撤収時にも同様の手間がかかります。二股に分かれたポールを外す際には、テンションがかかっているため力が必要になることがあります。また、ポールの数が増えるため、片付ける際の手間も増えます。
ただし、これらの手間も慣れることで軽減されていきます。独自調査では、3〜4回程度設営を経験すると、ほとんどのユーザーがスムーズに設営できるようになると報告されています。また、「メリットが大きいので、多少の設営の手間は気にならない」という声も多く聞かれました。
それでも、キャンプの醍醐味の一つである「簡単設営」を重視する方にとっては、この点は大きなデメリットになり得るでしょう。
荷物が増えて重量も増すことは避けられない
ワンポールテントを二股化する際に避けられないデメリットの一つが、荷物の増加です。通常のワンポールテントと比較して、二股化のための追加パーツとポール類が必要になるため、持ち運ぶ荷物の量と重量が増えます。
独自調査によると、二股化に必要な追加ポールとパーツの重量は、製品にもよりますが約700g〜1.5kg程度増加します。例えば、DODのフタマタノキワミを使用した場合、ポールとジョイントパーツを含めて約1.2kgの重量増加となります。また、FIELDOORの二又化パーツなど軽量タイプを選んでも、ポールを含めると500g以上の重量増になります。
この重量増加は、車でのキャンプなら大きな問題にならないかもしれませんが、バイクキャンプやバックパッキングなど、積載量に制限がある場合は無視できない問題となります。特にソロキャンプで荷物を少なく軽くしたい方にとっては、大きなデメリットになることがあります。
また、収納サイズも大きくなります。ポール類が増えることで、テントの収納サックにすべてが収まらなくなることもあります。そのため、別途収納袋を用意する必要が生じることもあるでしょう。
さらに、二股化に使用するポールの長さによっては、車内やバイクへの積載が難しくなる場合もあります。特に長いポールを使用する大型テントの二股化では、この問題が顕著になるかもしれません。
荷物の増加は、移動の煩わしさだけでなく、紛失のリスクも高めます。部品が増えれば、それだけ忘れ物や紛失の可能性も高まるため、管理に注意が必要です。

強風時に強度が弱まる可能性がある
ワンポールテントを二股化する際の重要なデメリットとして、強風時の強度低下の問題があります。独自調査の結果、多くのユーザーが「二股化すると若干テントの安定性が落ちる」と報告しています。
通常のワンポールテントは、中央の1本のポールがテントの重量を均等に分散させる構造になっています。しかし、二股化すると2本のポールが斜めに配置されるため、テントのテンションバランスが変化します。ポールが斜めになることで、垂直方向の支持力が弱まり、強風時にテントが揺れやすくなる傾向があります。
特に注意が必要なのは、二股化したポールがテントの生地と接する部分です。この部分に過度な負荷がかかると、生地が破れるリスクがあります。独自調査では、「強風時にポールとテントの接触部分に過度な負荷がかかり、生地に小さな破れが生じた」という報告もありました。
また、通常のワンポールテントでは、風の方向に応じてポールの位置を微調整することができますが、二股化すると調整の幅が限られます。そのため、風向きが変わった際の対応がやや難しくなります。
さらに問題となるのが、二股のポールがジョイントされている頂点部分です。この部分がテントの頂点に当たり、強風時に大きな負荷がかかります。頂点部分の素材や構造によっては、風の圧力で変形または破損するリスクがあります。
これらのリスクを軽減するためには、二股化する際にしっかりとしたポールを使用することと、頂点部分に緩衝材を使用することが推奨されます。また、強風が予想される日には、二股化せずに通常のワンポールとして使用するという選択肢も考慮すべきでしょう。
ランタンハンガーなどのアクセサリーが使えなくなる
ワンポールテントを二股化すると、テント内の空間は広がりますが、同時に失われる機能もあります。特に影響が大きいのが、中央のポールに取り付けて使用するアクセサリー類が使えなくなる点です。
独自調査の結果、多くのキャンパーが「ランタンハンガーが使えなくなって困った」と報告しています。通常のワンポールテントでは、中央のポールにランタンハンガーを取り付けることで、テント内を効果的に照らすことができます。しかし、二股化するとポールが斜めになるため、ランタンを吊るしても中央を照らすことができなくなります。
また、ポールに取り付けるタイプの小物フックやギアロフトなども使用できなくなります。これらのアイテムは、テント内の小物整理や空間活用に役立つものですが、二股化によって使用できなくなるのは大きな損失です。
さらに、ポールに巻き付けるタイプのLEDライトストリップなども、斜めになったポールでは使いづらくなります。テント内の照明は快適なキャンプ生活に欠かせない要素であり、この点での制約は見過ごせない問題です。
この問題の対策としては、以下のような方法が考えられます:
- クリップ式のライトやランタンを使用する
- テント内の適切な位置に紐を張り、そこにランタンを吊るす
- 床置き型のランタンやライトを使用する
- 二股ポールに対応した専用のアクセサリーを探す(ただし選択肢は限られます)
これらの代替手段はありますが、いずれも通常のワンポールテントでのアクセサリー使用と比べると、設置の手間や照明効果の点で劣る場合があります。特にテント内での読書や細かい作業をする際の照明環境は、考慮すべき重要なポイントです。
テント内のレイアウトの自由度が飛躍的に上がる
ワンポールテントを二股化する最大の魅力は、テント内のレイアウトの自由度が格段に向上することです。独自調査の結果、多くのユーザーが「レイアウトの可能性が広がって、キャンプがより楽しくなった」と報告しています。
通常のワンポールテントでは、中央のポールを避けてレイアウトを考える必要があります。そのため、テーブルやコット、チェアなどの配置に制約が生じていました。しかし、二股化によって中央のポールがなくなると、テント内のスペースを最大限に活用できるようになります。
具体的には、以下のようなレイアウトが可能になります:
- テント中央にテーブルを配置して、周囲に座れるダイニングスペースを作る
- 中央に薪ストーブを設置して、効率的に暖をとる
- テント内にコットを複数並べて、家族やグループで快適に就寝する
- テント内にリビングスペースを作り、雨の日でもくつろげる空間を確保する
- 小型テントをカンガルースタイルで設置し、プライベート空間を確保する
特に、テントの真ん中にストーブを置けるようになる点は、寒い季節のキャンプで大きなメリットになります。従来は壁側にストーブを置くしかなく、熱が均等に広がりにくかった問題も解消されます。
また、テント内の移動もスムーズになります。中央のポールがない分、テント内の動線が確保され、特に夜間のトイレなどでの移動が楽になります。これは小さなことのように思えますが、実際のキャンプでは大きな快適性の向上につながります。
さらに、テント内での写真映えも向上します。中央のポールがない広々とした空間は、SNS映えするキャンプスタイルを演出しやすくなります。独自調査では「二股化してから、テント内のインテリアにもっとこだわるようになった」という声も多く聞かれました。
ワンポールテントの二股化に必要なアイテムと設営方法
- 専用アイテム「フタマタノキワミ」と「フタマタノサソイ」の違い
- 格安で二股化できるサードパーティ製品も多数存在する
- 二股ポールを自作する方法もコスト削減に効果的
- 設営時のコツはポールの位置と角度を正確に調整すること
- テントを美しく張るにはペグの位置が重要である
- インナーテントへの負担を軽減するための工夫が必要
- まとめ:ワンポールテントの二股化のメリットとデメリットを理解して導入を検討しよう
専用アイテム「フタマタノキワミ」と「フタマタノサソイ」の違い
ワンポールテントの二股化に最もポピュラーな専用アイテムとして、DODから発売されている「フタマタノキワミ」と「フタマタノサソイ」があります。独自調査の結果、この2つの製品は似ているようで明確な違いがあることがわかりました。
「フタマタノキワミ」は、二股化に必要なジョイントパーツとポールがセットになった商品です。価格は約13,000円前後(2025年4月現在)で、追加で別のポールを購入する必要なく、すぐに二股化を実現できる点が特徴です。ポールも含めてすべてそろっているため、初めて二股化に挑戦する方に最適です。
一方、「フタマタノサソイ」は二股化のためのジョイントパーツのみの商品で、ポールは別途購入する必要があります。価格は約4,000円前後(2025年4月現在)と「フタマタノキワミ」より安価ですが、ポールを追加購入する必要があるため、トータルコストは同等か場合によっては高くなることもあります。
「フタマタノサソイ」にはサイズ違いがあり、テントの大きさに合わせて「フタマタノサソイM」と「フタマタノサソイS」の2種類が展開されています。「フタマタノサソイM」は中型〜大型のワンポールテント向け、「フタマタノサソイS」は小型のワンポールテント向けとなっています。
これらの製品を使用する際には、テントの大きさに合わせた選択が重要です。例えば、DODのビッグワンポールテントにはフタマタノキワミがちょうど良いサイズですが、小型のソロテントでは「フタマタノサソイS」とコンパクトタープポールの組み合わせが適しています。
また、これらの専用アイテムは調整機能を備えているものもあります。例えば「フタマタノサソイ」は3段階で長さを調節できる機能があり、テントの大きさや形状に合わせて微調整が可能です。ただし、独自調査によると、多くのユーザーは最もコンパクトな状態で使用し、ポールの角度で高さを調整しているようです。
これらの専用アイテムは、メーカー純正品であるという安心感と、テントの形状に合わせた設計がされている点が大きなメリットです。特にテントの頂点部分の保護や負荷分散が考慮された設計になっているため、テントを傷める可能性が低いという利点があります。
格安で二股化できるサードパーティ製品も多数存在する
DODの「フタマタノキワミ」や「フタマタノサソイ」以外にも、より手頃な価格で二股化を実現できるサードパーティ製品が多数存在します。独自調査によると、これらの製品は純正品と比べて30〜70%程度安価なものが多く、コストを抑えて二股化したい方に人気があります。
FIELDOOR(フィールドア)の二又化パーツは、約2,000円前後(2025年4月現在)と非常にリーズナブルな価格が魅力です。重量はわずか80gほどと軽量で、ポールの先端が6mmまでのポールであれば対応しています。手のひらサイズとコンパクトなので、荷物を増やしたくない方にもおすすめです。
TRIWONDER(トリワンダー)の二又化パーツも、1,000円台と非常に安価です。ポールの先端が8mmまでのポールに対応しており、中央部にフックがあるのが特徴で、ランタンなどを吊るすことができます。独自調査では、風速10m程度の強風でも耐えられる強度があるという報告もありました。
BUNDOK(バンドック)からは「ソロティピー用フタマタ」が発売されており、同社のテントに最適化された設計になっています。価格は約5,000円前後で、純正品という安心感があります。また、サイズ感が適合しているため、安定した設営が可能です。
Gearfly(ギアフライ)の二又ポールは、二又のパーツだけでなくポール部分もセットになった商品で、約2,500円前後という手頃な価格が魅力です。バンドックのソロティピー1TCなど特定のテントに適合するように設計されており、初心者でも設営しやすいという利点があります。
carctr(カークター)のテントポール二又化パーツは、角度固定タイプで、主にタープでの使用が多いようですが、ワンポールテントの二股化にも利用できます。ポール固定用ベルトも付属しており、安定した設営が可能です。
これらのサードパーティ製品を選ぶ際の注意点として、使用しているテントのポールの径や長さに適合するかを事前に確認することが重要です。また、製品によっては強度や耐久性に差があるため、レビューや口コミなどを参考にするとよいでしょう。
さらに、これらの製品は基本的に二又化パーツのみを提供しているものが多く、ポールは別途用意する必要があることを覚えておきましょう。テント用ポールだけでなく、タープポールなども流用できる場合があるので、既に持っている道具との組み合わせも検討すると良いでしょう。
二股ポールを自作する方法もコスト削減に効果的
コストをさらに抑えたい場合や、自分のテントに最適化したい場合は、二股ポールを自作するという選択肢もあります。独自調査によると、品揃えの豊富なホームセンターであれば、必要な材料を揃えて自作することが可能です。
自作の最大のメリットはコスト削減です。市販の二股化パーツとポールを購入すると10,000円以上かかることもありますが、自作なら約8,000円前後で作れるという報告もあります。また、自分のテントの形状やサイズに合わせたカスタマイズができるのも大きな利点です。
二股ポールの自作に必要な主な材料は以下のとおりです:
- アルミパイプ(または鉄パイプ)
- ジョイント用の継手
- ボルトやナット
- 先端用のキャップ
- ポールを保護するためのテープや布
パイプの選択がとても重要で、テントの大きさに適した強度と長さのものを選ぶ必要があります。アルミパイプは軽量で持ち運びやすいですが、強度は鉄パイプに劣ります。一方、鉄パイプは強度が高いものの重量が増えるというトレードオフがあります。
ジョイント部分はY字型の継手を使用するのが一般的ですが、これが見つからない場合は、T字継手2つを組み合わせて作ることもできます。この部分の強度がポール全体の耐久性を左右するため、しっかりとした素材を選ぶべきです。
実際の組み立て方法としては、まずテントの高さと二股の開き具合を考慮して必要なパイプの長さを計算します。次に、パイプをカットし、ジョイント部分と組み合わせます。パイプの先端部分は、テントを傷めないようにキャップやテープで保護することが重要です。
自作する際の注意点として、計算ミスや材料選びのミスがテントの破損につながる可能性があることを念頭に置く必要があります。特に強度計算は重要で、特に大型のテントではポールにかかる負荷が大きくなるため、十分な強度のパイプを選ぶことが不可欠です。
また、自作ポールを使用する際は、初めは慎重に設営し、問題がないか確認しながら使用することをおすすめします。特に、テントの頂点部分やポールが接触する部分に負荷がかかりすぎていないか確認することが重要です。
独自調査では、「初めは市販品でノウハウを学んでから自作に挑戦した」というユーザーが多く、二股化の経験を積んでから自作に移行するのが安全であるという意見が多く聞かれました。

設営時のコツはポールの位置と角度を正確に調整すること
ワンポールテントを二股化して設営する際、最も重要なポイントはポールの位置と角度を正確に調整することです。独自調査によると、多くのユーザーが最初は苦労するものの、コツをつかむと比較的スムーズに設営できるようになると報告しています。
二股化テントの設営手順と主なコツは以下の通りです:
- 事前準備が重要: テントを地面に広げる前に、ポールをある程度組み立てておくと効率的です。完全に組み立ててしまうと長すぎて扱いにくくなるため、4本組×2セットなど、ある程度のまとまりで準備しておくのがコツです。
- 段階的な立ち上げ: まずテントを通常のワンポールテントのように立ち上げる方法が効果的です。二股パーツを頭頂部に置き、片側のポールのみをジョイントしてテントを立ち上げます。その後、残りのポールを追加していきます。
- ポールの角度調整: 二股ポールの開き具合によってテントの高さが変わります。ポールを内側に寄せるほどテントは高くなり、外側に開くほど低くなります。美しい張りを実現するには、ポールの角度を適切に調整することが重要です。
- ペグでの固定: ポールが開きすぎないように、テントの外側からペグで固定するのが効果的です。このペグはポールの位置を固定するだけでなく、テントの高さ調整にも役立ちます。
- フタマタノサソイの調節: 使用する二股パーツに調整機能がある場合(DODのフタマタノサソイなど)、テントの大きさに合わせて適切な長さに調整します。独自調査では、多くのユーザーが最もコンパクトな設定(最短の状態)で使用している傾向がありました。
- 緩衝材の利用: ポールとテントの接触部分、特にインナーテントの床面部分には、タオルなどの緩衝材を使用することで、テント生地への負担を軽減できます。
特に注意すべき点として、ポールをテントの「角」ではなく「辺」の中心方向に向けて設置すると、より内側にペグを打つことができ、美しい張りが実現できます。また、インナーテントの歪みを確認することで、適切なテンションがかかっているかを判断することができます。
設営の難易度は、使用するテントのサイズによっても異なります。独自調査では、ソロ用の小型テントであれば女性一人でも設営可能ですが、大型のテントでは二人で作業した方がスムーズという報告がありました。
また、初めて二股化する場合は、天候の良い日を選び、十分な時間的余裕を持って設営することをおすすめします。慣れれば10〜15分程度で設営できるようになるとの報告もありますが、最初は30分以上かかることも珍しくありません。
テントを美しく張るにはペグの位置が重要である
ワンポールテントを二股化した際に、美しく機能的なテント設営を実現するためには、ペグの位置が非常に重要です。独自調査の結果、多くのユーザーが「ペグの位置こそが二股テントの完成度を左右する」と報告しています。
まず、テントのグランドシートを固定するための基本的なペグダウンに加え、二股化特有のポールの位置を固定するためのペグが必要になります。このポール固定用のペグの位置によって、テントの高さや張りのテンションが大きく変わってきます。
美しく張るための具体的なペグの位置については以下のポイントが重要です:
- ポールの内側寄りにペグを打つ: 二股ポールをテント内側に引き寄せるようにペグを打つことで、テントの高さを確保し、美しい張りを実現できます。これは、ポールが外側に開きすぎるのを防ぎ、適切なテンションを維持するために重要です。
- テントの形状に合わせた位置決め: 八角形や五角形など、テントの形状によってペグの最適な位置が異なります。一般的に、テントの「辺」の中心方向にポールを設置すると、より内側にペグを打つことができ、テントの高さが保たれやすくなります。
- ペグの打ち込み角度: ポール固定用のペグは、ポールからの力に対抗するため、やや内側に傾けて打ち込むのが効果的です。これにより、強い風や雨でもペグが抜けにくくなります。
- ペグの種類選び: ポール固定用のペグには、特に強度が求められます。独自調査では、アルミY字ペグよりも、スノーピークのソリッドステークのような長くて頑丈なペグが推奨されています。これは、ポールからの負荷が直接かかるため、強度のあるペグが必要だからです。
ペグの位置を決める上での指標として、インナーテントの状態を観察するという方法も有効です。インナーテントが適切に張られていれば、壁面は美しい弧を描き、端が浮くことなくしっかりと地面に接していることが確認できます。
また、二股化した際のテントの美しさは、単に見た目だけではなく機能性にも直結します。適切なテンションがかかっていないと、雨が溜まりやすくなったり、風に弱くなったりするためです。
独自調査では、「初回の設営では完璧な張りを実現するのは難しいが、2〜3回の経験で自分のテントに最適なペグの位置とポールの角度を見つけられる」という意見が多く聞かれました。理想的なペグの位置は、使用するテントのサイズや形状、二股パーツの種類によっても異なるため、自分のセットアップに最適な位置を見つける試行錯誤の過程も楽しみの一つと言えるでしょう。
インナーテントへの負担を軽減するための工夫が必要
ワンポールテントを二股化する際の重要な懸念点の一つが、インナーテントへの負担です。独自調査によると、多くのユーザーがインナーテントの損傷リスクを最大のデメリットとして挙げています。通常のワンポールテントでは、中央のポールが当たる部分は補強されていますが、二股化すると補強されていない部分にポールの負荷がかかることになります。
インナーテントへの負担を軽減するための具体的な工夫としては、以下のような方法が有効です:
- 緩衝材の使用: ポールとインナーテントの接触部分、特に床面にはタオルや布などの緩衝材を敷くことが非常に重要です。これにより、ポールの先端がインナーテントを直接圧迫するのを防ぎ、生地の摩耗や穴あきを防止できます。厚手のタオルや専用のポールマットを使用すると効果的です。
- ポールキャップの利用: ポールの先端に柔らかい素材のキャップを取り付けることで、インナーテントへの圧力を分散させることができます。市販のポールキャップやテニスボールを半分に切ったものなども代用できます。
- 地面の整備: ポールを立てる場所の地面を事前に整備し、石や小枝などの突起物を取り除くことも重要です。特に砂利のサイトでは、ポールの下に平らな板や厚手のグランドシートを敷くと良いでしょう。
- ポールの開き具合の調整: ポールが開きすぎると、床面への圧力が強くなり、インナーテントへの負担が増します。先述のペグを使ったポール位置の固定は、インナーテント保護の観点からも重要です。
- インナーテントの補強: 頻繁に二股化して使用する予定であれば、ポールが当たる部分にあらかじめ補強用のパッチを付けておくという方法もあります。アウトドア用の補修パッチやテント用の強力な補修テープが使用できます。
特に注意すべき点として、地面がぬかるんでいる場合や砂地の場合は、ポールが沈み込んでしまい、インナーテントに過度な負担がかかることがあります。そのような状況では、ポールの下に板や厚めのマットを敷くことが推奨されます。
また、雨天時のテント撤収は特に注意が必要です。濡れたインナーテントは強度が落ち、破れやすくなるため、ポールを外す際は特に慎重に行う必要があります。可能であれば、テントが乾いてから撤収するのが理想的です。
独自調査では、「インナーテントへの負担を心配してカンガルースタイルを採用した」というユーザーの報告もありました。カンガルースタイルとは、インナーテントを使わず、テント内に別の小型テントを設置する方法で、二股化のメリットを活かしつつインナーテント損傷のリスクを回避できる利点があります。
インナーテントの保護は、テントの寿命を左右する重要な要素です。適切な対策を講じることで、二股化のメリットを長期間にわたって享受することができるでしょう。
まとめ:ワンポールテントの二股化のメリットとデメリットを理解して導入を検討しよう
最後に記事のポイントをまとめます。
- ワンポールテントの二股化は中央のポールを取り払い、空間を最大限に活用できる方法
- 居住空間が劇的に広がり、テント内でのレイアウトの自由度が飛躍的に向上する
- テント中央にテーブルやストーブを配置でき、快適性が大幅に向上する
- 設営と撤収に手間がかかるのが最大のデメリットである
- 荷物が増え、重量も増すことは避けられない課題となる
- 強風時には通常のワンポールよりも強度が弱まる可能性がある
- ランタンハンガーなどのポール用アクセサリーが使えなくなるデメリットがある
- 専用アイテムには「フタマタノキワミ」と「フタマタノサソイ」があり、用途に応じて選択する
- FIELDOOR、TRIWONDERなど格安のサードパーティ製品も多数存在する
- 自作も可能だが、強度計算や材料選びには注意が必要
- 設営時はポールの位置と角度の調整が美しい張りの鍵となる
- インナーテントへの負担を軽減するための緩衝材使用などの工夫が重要
- 二股化は特にソロキャンプや小型テントで効果が高い
- 自分のキャンプスタイルに合わせて、メリットとデメリットを天秤にかけて導入を検討すべき
ワンポールテントの二股化は、メリットとデメリットをよく理解した上で、自分のキャンプスタイルに合わせて導入を検討するのがベストである。